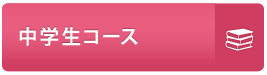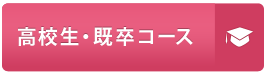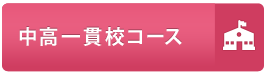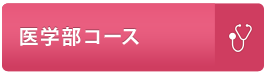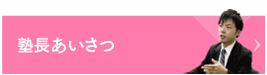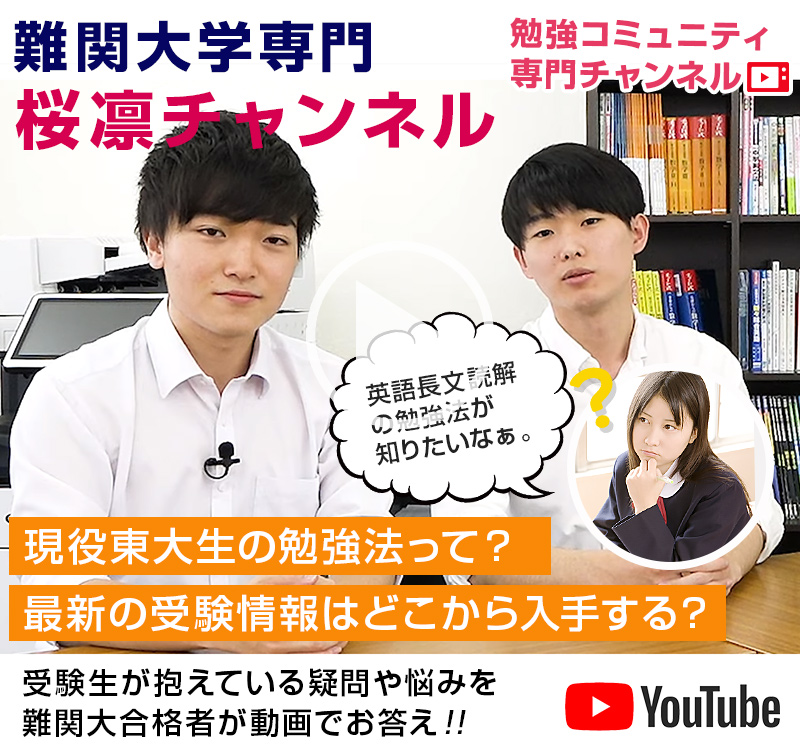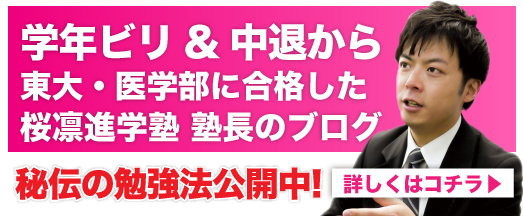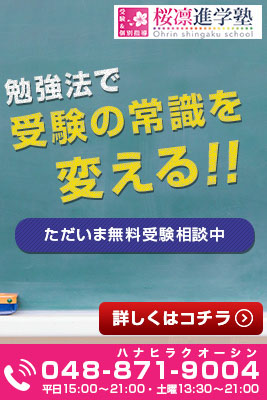理科の仕上げはここから!物理の頻出分野を総チェック

こんにちは!桜凛進学塾浦和校です。
いつもご覧いただきありがとうございます。
共通テストまで残りわずか。10月に入ると、いよいよ理科の仕上げに突入する時期です。物理は得意不得意がはっきり出やすい科目ですが、頻出分野を効率よく押さえることで得点アップにつなげることができます。今回は、共通テスト物理で狙われやすい重要テーマと、10月からの勉強法を整理してご紹介します。
力学は最重要!「運動方程式」と「エネルギー保存則」
物理の中でも最も配点比率が高く、毎年必ず出題されるのが力学です。特に、運動方程式の立式や力のつり合いは、得点差がつくポイント。
また、エネルギー保存則と運動量保存則は典型問題の宝庫です。摩擦がある場合や斜面運動、衝突や弾性力を含む問題など、条件を少し変えただけで難易度が上がります。
10月の段階では、基礎的な法則をただ「知っている」だけでなく、図を描いて状況を整理し、式に落とし込めるかどうかを意識して演習してみましょう。
波動は頻出!「干渉・ドップラー効果」に注目
波動分野も共通テストで毎年問われるテーマです。中でもヤングの干渉実験、光の回折・干渉、ドップラー効果は定番です。
特にドップラー効果は、「音源が動く場合」「観測者が動く場合」で式の使い分けを正確にできるかが得点の分かれ目。公式暗記だけではなく、波のイメージを頭の中で思い描けるかが大切です。
10月のうちに演習問題を繰り返し、公式を当てはめるだけでなく、「なぜその式になるのか」を理解しておくと、本番で応用問題が出ても対応できます。
電磁気は応用範囲が広い!「電磁誘導」と「コンデンサー」
電磁気分野は、計算に手間がかかる問題が多いため苦手とする受験生が少なくありません。ですが、共通テストではパターンが決まっており、対策が立てやすい分野でもあります。
特に電磁誘導(ファラデーの法則)は頻出で、「磁束の変化をどう数式に表すか」を問う問題が多いです。また、コンデンサーは電荷や電位差の関係を理解しているかどうかが試されます。
複数のコンデンサーを直列・並列につないだときの合成容量や、極板の間に誘電体を挿入したときの変化など、典型的な問題を繰り返し演習しておきましょう。
熱力学と原子分野は効率重視
近年の共通テストでは、熱力学(気体の状態方程式、熱力学第一法則)や原子分野(光電効果・原子核反応)も安定して出題されています。これらは複雑な計算というより、基本法則を正しく適用できるかを確認するような問題が中心です。
例えば、熱力学なら「気体が断熱変化する場合」「等温変化する場合」の区別を整理することが大切です。
原子分野では、光のエネルギーを「E=hf」で扱えるかどうか、核反応式の質量欠損とエネルギーの関係を理解しているかを押さえましょう。時間対効果を考えると、10月はまず標準レベルの基礎事項を一通り確認しておくのがおすすめです。
10月の学習法のポイント
典型問題の解き直し
新しい問題集に手を出すよりも、今まで解いた模試や問題集をもう一度解き直す方が効果的です。特に間違えた問題にマークをつけ、3回以上繰り返すことで「確実に解ける」状態にしましょう。
図を描いて考える習慣を徹底
共通テスト物理は、文章で状況を説明する形式が多いので、頭の中だけで処理しようとすると混乱します。必ず図を描き、力やエネルギーの流れを「見える化」しましょう。これにより問題の構造が理解しやすくなります。
模試を共通テスト本番のシミュレーションにする
10月以降の模試は、時間配分の練習の場でもあります。得意分野から解く、計算に時間がかかりそうなら後回しにするなど、自分なりの戦略を立てて挑むことが大切です。
まとめ
物理は「公式暗記科目」ではなく、「状況を理解し、法則をどう当てはめるか」を問う科目です。10月は、力学・波動・電磁気を中心に、頻出分野を確実に仕上げることを意識しましょう。そして模試や過去問を活用し、解法を身につけることで本番の得点力に直結します。
桜凛進学塾浦和校では、生徒一人ひとりの弱点を分析し、成績向上に繋がるように日々指導を行っています。残り時間を大切に、最後まで粘り強く取り組んでいきましょう!
桜凛進学塾浦和校のご案内
桜凛進学塾浦和校は、優秀な講師陣が「勝ちグセ」のつく勉強法を教えてくれる個別指導塾です。我々桜凛進学塾浦和校は目標に向かって突き進む皆さんを全力でサポートしていますね!
「勉強のやり方がわからない!」「高みを目指したい!」「志望校に合格したい!」という皆さんは、ぜひ一度、無料相談にいらしてくださいね!
浦和校
048-767-4450
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3−6−18 けやきビル7F